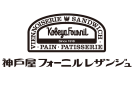クリスマスの由来は?意外と知らない起源や風習の意味を解説
クリスマスは年に1度の特別な日です。しかし、クリスマス本来の意味や由来について知らないという方も多いのではないでしょうか。当記事ではクリスマスの由来について解説しています。風習や食べ物の由来についても記載しているのでぜひチェックしてみてください。

日本におけるクリスマスと言えば、友人とパーティをしたり、恋人と素敵な時間を過ごしたり、家族と美味しい料理を食べたりなど、 親しい人と楽しい時間を共有する特別な日というイメージが強いと思います。 しかし、中には「クリスマスって本当はどのような日なの?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。 当記事ではクリスマスの由来について解説します。クリスマスの本来の意味や、 サンタクロースやクリスマスツリーなどの関連する風習の由来などもお伝えしています。クリスマスをさらに楽しむためにも、ぜひ最後までご覧ください。
クリスマスとは?意味や由来について
クリスマスとは本来どのような日なのでしょうか。ここではクリスマスの意味や由来、クリスマス・イブの位置付けなどについて解説します。
クリスマスは「イエス・キリスト」の降誕祭
クリスマスとは、イエス・キリストの生誕を祝う日のことです。「クリスマス=キリストの誕生日」と勘違いしやすいですが、 正しくはキリストが生まれたことをお祝いする「降誕祭」という意味を持ちます。ちなみに新約聖書ではキリストの誕生日は特定しておらず、具体的な日付は定かではありません。 また、クリスマスは英語で「Christmas」と表記します。これは「Christ(キリスト)」+「mas(ミサ、礼拝)」を組み合わせた言葉となっており、 キリストに祈りを捧げるという特別な意味を持ちます。「Xmas」という表記もよく目にしますが、これはギリシャ語でキリストを表す「Xristos」の頭文字に由来しているという説が有力です。
クリスマスが12月25日である理由
クリスマスが12月25日である理由は、諸説あります。 一説では、キリスト教がまだ定着していない時代に広く伝わっていたミトラス教という宗教が関わっていると言います。 太陽神を信仰するミトラス教では、1年で最も太陽が遠のき、昼間が短い日である冬至に「光の祭り」と呼ばれる行事を開いていました。 そして冬至以降、だんだんと太陽が近づき、昼間が長くなる様子を「太陽の復活」と称して祝っていたと言います。この光の祭りが行われていた日付が12月25日です。 そしてローマ帝国ではキリストを光(太陽)と比喩し、「太陽の復活=キリストの復活」として光の祭りを行っていた12月25日をキリストの降誕祭、つまりクリスマスに制定したと言われています。
クリスマス・イブとは
クリスマス・イブとは、クリスマスの前日にあたる12月24日のことです。イブは「イブニング(夜)」を指し、 直訳すると「クリスマスの夜」を意味します。つまり本来の意味では、クリスマスの前日ではなくクリスマス当日の夜を指すことになります。 これはキリスト教の起源であるユダヤ教において、日没~日没までを1日と数えていたことが影響しています。 つまり、ユダヤ教の暦の数え方ではクリスマスは「12月24日の日没~12月25日の日没まで」を指し、この期間でクリスマスの夜に当てはまるのが「12月24日の日没~深夜」。 そのため、12月24日がクリスマス・イブとなります。
クリスマスのイベントや風習の由来について
クリスマスには、サンタクロースからのプレゼントや、クリスマスツリーの飾り付けなど、特別なイベントや風習があります。それぞれの由来について解説します。
サンタクロースの由来
サンタクロースのモデルは、キリスト教の聖人である「聖ニコラウス」に由来すると言われています。 聖ニコラウスは英語で「セント・ニコラウス」、オランダ語で「シンタ・クラース」と呼ばれており、これがサンタクロースという名称の由来です。 また、サンタクロースからプレゼントを貰うという風習は、聖ニコラウスのある逸話が関係していると言われています。 聖ニコラウスが貧しい家の窓から金貨を投げ入れたところ、暖炉の近くにあった靴下の中に入ってしまったそうです。 それからクリスマスに靴下を用意しておくと、サンタクロースがプレゼントを入れてくれるという風習が広まったと言います。
クリスマスツリーの由来
クリスマスツリーは、古代ゲルマン民族のある信仰に由来するという説があります。 ゲルマン民族は冬の寒さにも負けない樫(かし)の木を、生命の象徴として祀っていました。 そしてゲルマン民族にキリスト教を普及させようとした宣教師が、樫の木の代わりに樅(もみ)の木を信仰する習慣を広めていったと言います。 また、一説では宣教師が樫の木を切り落としたところに、樅の木が生えてきたという逸話もあります。
クリスマスケーキを食べる由来
クリスマスケーキは、クリスマスを祝って食べるケーキ、つまりキリストの生誕を祝うバースデーケーキとして食べられるようになったと言います。 日本ではイチゴのショートケーキを用意するのが定番ですが、国によってクリスマスケーキは大きく異なります。 例えばドイツならシュトレン、フランスならブッシュドノエル、イタリアならパンドーロなど、国ごとに独自の文化を持っているのが特徴です。
クリスマスの食べ物の由来とは?
クリスマスの楽しみの1つと言えば、美味しい食べ物の数々です。ここではクリスマス定番の料理・スイーツの由来について解説します。
七面鳥の由来
七面鳥はクリスマスシーズンになると、ローストターキーやターキーレッグとして食卓に並びます。 もともとは大航海時代にアメリカ大陸の先住民が、食糧難に陥っていた移民たちに七面鳥を振る舞ったことがきっかけで、 感謝の気持を込めて感謝祭やクリスマスに食べられるようになったと言われています。なお、日本では七面鳥ではなく鶏(チキン)を食べるのが一般的です。 ▼クリスマスと七面鳥の詳しい解説はこちら 『なぜクリスマスに七面鳥を食べる?その起源やおすすめ料理などを解説』
シュトレン(シュトーレン)の由来
シュトレンは、クリスマスシーズンに食べられるドイツの伝統的なスイーツパンです。かつてパン職人のギルドがクリスマスの贈り物として、司教に献上したと言われています。 また、粉砂糖がまぶされたシュトレンの真っ白な見た目が、「白いおくるみに包まれた幼いキリスト」を想起させることから、クリスマスに食べられるようになったという説も有名です。 ▼神戸屋でもクリスマス限定でシュトレンを販売中です。
▶シュトレンの詳細は、
こちら
ブッシュドノエルの由来
フランス発祥のクリスマスケーキとして有名なのが、ブッシュドノエルです。直訳すると「クリスマスの薪」を意味するように、 薪や丸太のような見た目をしています。一説では、キリストの誕生を祝うために一晩中、暖炉に薪をくべていたことが形の由来となったと言われています。 神戸屋では、シュトレンやブッシュドノエルなどの各種ケーキ、パーティ料理のご予約をクリスマス限定で承っております。 クリスマスの食卓を彩る特別なスイーツ・料理をぜひご家庭でお楽しみください。
▶クリスマス限定のケーキ・パーティ料理の詳細は、
こちら
【神戸屋おすすめ商品】クリスマス限定の「飾りパンオーナメント」をご紹介
クリスマスの雰囲気をより華やかなものにするために、自宅やクリスマスツリーの装飾にこだわってみるのもおすすめです。 神戸屋ではクリスマス限定で「飾りパンオーナメント」を販売しております。 飾りパンとは「パン・アーティスティック」とも呼ばれており、パンを模したヨーロッパの伝統的なオブジェのことです。 クロワッサンやプレッツェルなどの形が特徴的なパンも、ディティールにこだわって作られています。 クリスマス限定の飾りパンオーナメントは、全16種類をご用意。 ご自宅のクリスマスツリーに飾り付けるだけで、焼き立てのパンの香りを感じられるような温かな空間を作り出せます。 例年とは一味違うクリスマスを過ごしたい方は、神戸屋自慢の飾りパン職人が手掛けたクリスマス限定飾りパンオーナメントをぜひお取り寄せください。
▶飾りパンオーナメントのご購入は、
こちら
※クリスマス限定の販売となります。
▶飾りパンの詳細は、
こちら
由来を知ってクリスマスをさらに楽しもう
冒頭でもお伝えしたように、日本におけるクリスマスとは家族や恋人と素敵な時間を共にしたり、知人や友人と賑やかに過ごしたりと、楽しみ方は人それぞれです。 しかし、クリスマスの意味や関連する風習の由来を知ると、歴史的な背景や外国の文化を踏まえた上でクリスマスを過ごせるようになり、また違った雰囲気を感じられるようになります。 ぜひ今年のクリスマスは、当記事で紹介した情報を思い出しながら、素敵なクリスマスを過ごしてみてはいかがでしょうか。